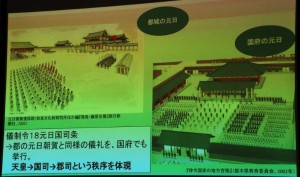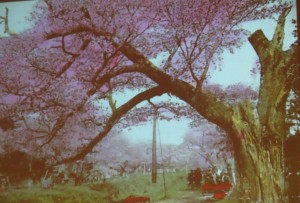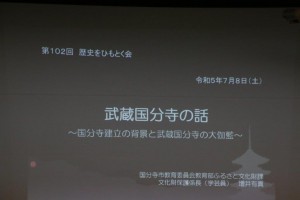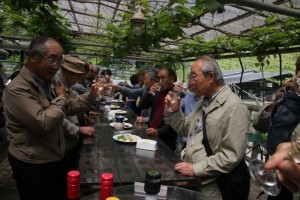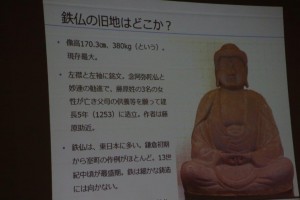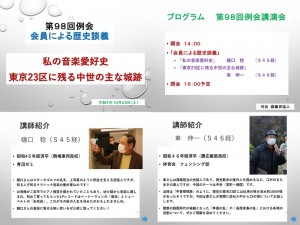武蔵国分寺の話
〜国分寺建立の背景と武蔵国分寺の大伽藍〜
7月8日(土)、国分寺本多公民館視聴覚室において、第102回例会が開催され、蒸し暑い中ではあったが、37名の方が参加された。
 講師は国分寺市教育委員会ふるさと文化財課文化財保護係長(学芸員)の増井有真氏。先生は国分寺市の文化財保護と普及活動の中心となって活動しておられ、武蔵国分寺跡史跡指定100周年記念事業を中心となって推進された。歴史をひもとく会においても、2019年の2月23日の第88回例会で「武蔵国分寺以前の歴史~古墳時代から律令時代の黎明期を中心として~」と題してご講演いただいている。
講師は国分寺市教育委員会ふるさと文化財課文化財保護係長(学芸員)の増井有真氏。先生は国分寺市の文化財保護と普及活動の中心となって活動しておられ、武蔵国分寺跡史跡指定100周年記念事業を中心となって推進された。歴史をひもとく会においても、2019年の2月23日の第88回例会で「武蔵国分寺以前の歴史~古墳時代から律令時代の黎明期を中心として~」と題してご講演いただいている。
ご講演内容要約
国分寺建立の意味を考える際には、なぜ建てられたか、そして人々がどのような思いをかけたのかが重要である。
それを知るためには、7〜8世紀の時代背景を知る必要がある。7世紀は豪族の連合政権に近かった4〜6世紀の古墳時代から、一転中央集権を目指した時代といえる。また、同時に国家の基本的理念として仏教が採用されていった時代でもある。中央集権を国家目標とした契機は3つ考えられる。
一つ目は天皇をも凌駕しかねない巨大権力をもった豪族が出現、それを排除する必要があり、乙巳の変により中大兄皇子らが蘇我氏を滅ぼしたが、このような事態の再来を防ぐため、中大兄皇子は自ら権力を握り、皇親政治により中央集権を強化していった。
二つ目は白村江の戦いで唐・新羅の連合軍に敗北した結果、唐による日本列島侵攻が現実的な危機となり、中央集権的な軍事体制の創設が急務となった。
三つ目は壬申の乱という内戦により、皇位継承のルール確立が必要となり、そのためには強い中央政府が必要となった。
中央集権の制度的骨格となったのが律令制だが、その中で地方の行政制度も確立されてゆき、武蔵国が置かれることとなった。中央から派遣された国司が国全体を統括したが、国司がいるのが国庁、それを囲むように国衙が造られ、周囲の街並みを含めて国府と称した。
武蔵国は国の格としては大国であり、21郡がおかれ、当初は東山道に属したが後に東海道に転属した。武蔵国府は現在の府中市にあり、武蔵国府関連遺跡の範囲は東西6.5km、南北1.8kmに及ぶ。
このような時代背景の中、国分寺建立の中心となった聖武天皇が登場する。聖武天皇は藤原氏の血を引く初めての天皇である。乙巳の変の立役者の一人中臣鎌足が藤原の姓を与えられたことで、藤原氏は成立したが、聖武天皇は鎌足の息子不比等の娘宮子と文武天皇の間に誕生した。しかし、彼は幼少期、母親の宮子の病のため母親を知らずに育ったことや、天皇即位後、宮子に「大夫人」の称号を与える勅を出したものの、長屋王の反対により勅を撤回せざるを得ないという事件、藤原氏と長屋王の権力闘争から長屋王が死に追い込まれた長屋王の変を経験した上、その治世は飢饉や天然痘の流行、藤原広嗣の乱などが相次ぐ波乱にとんだものだった。彼はそれらの災厄を全て自身の不徳と捉え、自身を責め続けたが、国民の幸福実現のためには仏教の力が必要との結論にいたった。そして、741年2月国分寺建立の詔がだされた。
「・・・金光明最勝王経には『もし広く世間でこの経を読み、敬い供養し、広めれば、われら四天王は常に来てその国を守り、一切の災いもみな取り除き、心中にいだくもの悲しい思いや疫病もまた消し去る。そしてすべての願いをかなえ、喜びに満ちた生活を約束しよう』とある。そこで、諸国にそれぞれ七重塔一基を敬って造り、併せて金光明最勝王経と妙法蓮華経を各十部ずつ写経させることとする。私もまた、金文字で金光明最勝王経を写し、塔ごとに一部ずつ納めたいと思う。」
聖武天皇はその後、華厳経と出会ったことから、大仏建立へと向かっていった。
このようにして、武蔵国分寺は建立されることとなったが、四神相応の地であることと国府の街並みから適度に離れていなければならないことからこの地に造られたと考えられる。規模は寺地が東西2km。南北1.5km、僧・尼寺を含む寺院地が東西870m、南北540mで、この規模は、東大寺を除くと諸国の国分寺の中で最大である。
国ごとに官寺をおく制度は中国にもあるが、尼寺を置くのは日本独自のもので、光明皇后の発案だという説がある。聖武天皇の仏教による国家運営には光明皇后の影響は非常に大きかったと考えられる。
当初は七重塔を中心とするプランでスタートしたが、造営が進まないことに剛を煮やした聖武天皇が国司ではなく、郡司層を中心としたプロジェクトに変更、協力の見返りに郡司職の世襲を認めたことから、郡司層の積極的な関与が実現し、計画が拡大・加速され、すでに建設されていた七重塔より西に拡張された結果、現在確認されているようなプランとなった。七重塔は2回建て替えられたことが、発掘調査から判明しているが、1回目と2回目の間に場所を変えて建設しようとした跡なども調査により見つかっている。ただし、これは途中で断念されたらしい。七重塔以外の施設としては、金堂、講堂、中門、塀、南門、東僧坊、北方建物、鐘楼、堂間通路などが判明している。また、国分寺を支える施設として、政所院、大衆院、苑院、花園院、東院、中院、修理院、講師院などの施設の存在が明らかとなっている。
最盛期は9世紀で、10世紀中頃から11世紀にかけて衰退し、1333年の分倍河原の戦いの折に焼失したが、薬師如来は残って現在に伝えられている。途中、塀が掘立柱から築地塀に造り替えられるなど地震対策が見られる。
国分寺の造営は20年余りが費やされたと考えられるが、境界となる溝の総延長は7800m、延べ5850人を動員、使用された礎石は約500個、延べ17000人を動員、瓦の数は約50万枚、瓦工延べ6700〜7800人、仕丁延べ13400〜15600人が動員されたと考えられるが、当時の武蔵国の人口は約13万人と考えられるので、農民にはかなり大きな負担となったと考えられる。総工費は現代の貨幣価値に換算すると、848億5千万円という巨額になると試算されている。
以上が先生にお話の概要だが、要約しきれないほど詳細で、かつ先生の国分寺愛がこめられた情熱的な語りで、素晴らしいご講演であった。
講演会終了後、国分寺駅北口のデンズキッチンにて懇親会を開催した。懇親会には講師の増井様も出席され盛り上がった懇親会となりました。