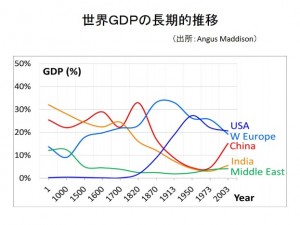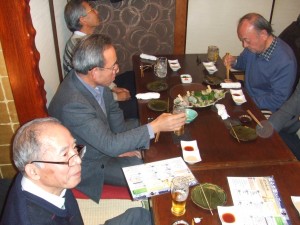【テーマ:地方自治~現場の苦悩と喜び~】
5月21日(日)、前国分寺市長、星野信夫さんを講師にお迎えし講演会を開催しました。開催場所も、星野さんにとっては市長時代に誘致を決めた思い出のある都立多摩図書館。天井も高く好環境の中で熱のこもった素晴らしい講演会でした。
講師は2001年に第5代国分寺市長に初当選され、以来2013年に退任されるまで、3期12年間の長期に亘り務められてこられました。まちづくりの理念として「共生、参加、創造」を、またスローガンとして「改革断行」を掲げて市政を担当してこられました。この間、「職員に支えられ市民に応援され市政を務められたと思う」と冒頭で述べられた感想が印象的でした。以下、就任当時の状況および大型事業への取り組みに的を絞り報告します。
記
市政を振り返り:
最初の仕事は地域に相応しい「都立武蔵国分寺公園」の命名であった。最初の難題となったのが西国分寺駅東地区の再開発事業である。この案件は西国分寺駅近くに市民文化会館を建設する事業であったが、建設の是非を巡って議論の末住民投票が実施され、結果僅かに反対が賛成を上回り、幾多の経過を経て市民文化会館建設計画は廃止され、民間のスポーツクラブが建設される事に変更された。
市政に関して:
市長は市民から直接選挙で選ばれるので大きな権限を持ち、様々な案件の提案権を持っているが、あくまで決定権は議会にある。また国分寺市政は初代より保守、革新の市長が毎回入れ代わり、長期開発案件を遂行するには困難が伴う状況にあった。加えて国分寺市は府中市や小平市等と異なり、大規模事業所がなく市の歳入は個人市民税が中心である事から、大きな開発案件の遂行は財政的に困難な下地がある。一方、国分寺市の人口は市設立の当初5万6千人であったものが、高度成長期の波に乗り都内からの移動も多く人口が急激に増加し、現在は3倍の12万人に達している。こうした人口増加により下水道の整備・学校建設・ごみ処理施設の整備が急がれた。下水道の整備等では多額な借金を余儀なくされたが、バブルの崩壊と共に経済環境が悪化した為、多額の借入金返済に追われ、開発案件の計画・遂行上大きな障害となった状況がある。バブル崩壊後の失われた20年は国・地方の財政を著しく悪化させたが、実にその内の12年間が星野市政の期間でもあった。更に急速な少子高齢化が進み社会保障費が増大した時期にも重なっている。
国分寺駅北口再開発事業では:
1965年初代市長の代に最初の計画が掲げられたが、反対が多く長期に亘り進展がなかった。その間「開発よりも福祉優先」等の声が大きく挙がっていたが、星野市長は当再開発事業を継承し進める事とした。事業を進める上で大きな問題は地域に187名もの多くの権利者がおり、権利調整が難航した事であるが、その上2001年から始まったITバブルの崩壊が税収の大幅低下を招いた事が追い打ちをかける事となった。
一方、下水道の整備は開発工事と同時に着手すべきとの考え方から、駅周辺の下水道 が未整備状態にあり、一刻も早く開発工事を進める必要に迫られていた。更に万一開発を止める様な事になれば、損害賠償の問題等も発生する恐れがある為、事業の中断は許されず、如何に計画変更で難局を乗り越えられるかに焦点が絞られた。解決案として出されたのが、建物の建設場所を駅の近くに移し、建物の価値を高める事により商業床の販売収益を増加させ、以て開発費用の確保をする事であった。これにて一件落着と思いきや、またもやリーマンショックにより商業床が売れない事態が発生した。この問題については、「建物のスリム化と高層化」、且つ「商業床の多くを住宅床に変更」する事で開発事業は成功する目途が立った。市の想定を大幅に上回る額で落札され、建物除却の予算をつけてバトンタッチした。
ごみ処理の問題では:
複数の自治体で焼却炉を持つ場合は東京都から補助金が出る事や、大きな焼却炉設置による経済性、環境整備、自家発電設備保有等の利点がある事から平成16年、小金井市からの依頼により国分寺市と共同でゴミ処理する為の協議を開始した。
小金井市からは平成20年3月までに二枚橋近くにゴミ焼却場用地を確保する旨、またそれまでの間、小金井市のゴミを国分寺で処理願いたいとの申し出であった。しかし用地確定が出来ず問題が発生した。最終的に日野市長の決断により、国分寺及び小金井両市のゴミを受け入れる事で決着する事になった。当時日野市長はこの決断により逆に住民からの批判を招く事にもなったが、正しく日野市長の英断により難局が解決された次第である。
尚、日野市及び小金井市はゴミの減量化で現在全国一の優良自治体と言われているが、国分寺市は未だその域に至っていない。
都市計画道路整備について:
国分寺駅から北に登り、本多公民館の辺りで交わる道路が3・4・6号線(東西道路、日立中央研究所北川の道路)であるが、この道路は日本で一番時間がかかっている都市計画道路と言われている。新しい計画で道路が鉄道と交差する場合、立体交差とすべき事が道路法で定められている。この道路は西武線2本と交わるが、道路立体化には多額の費用がかかる為、都とも相談しながら進めているが、今後に残された課題もある。
都道3・2・8号線(南北道路、新府中街道)は中央線・西武線交差部分以外平面交差に改め計画推進中。この道路では小平市での反対運動は住民投票迄実行されたが、一応の決着を見ている。
講演出席者の質問に応え下記発言された事が印象に残っている:
大学は慶應義塾の経済学部、加藤寛ゼミで経済政策を勉強した。強く印象に残っている先生の言葉は、「マルクスは間違っていた。しかし、政策を論ずる者はマルクスの社会を変えて行こうとする社会的情熱に学ばなければならない」という言葉であった。
講演会後:
西国分寺駅近くの居酒屋に20名が集まり、大いに盛り上がった一日でした。
-

-

-

-

-
懇親会1